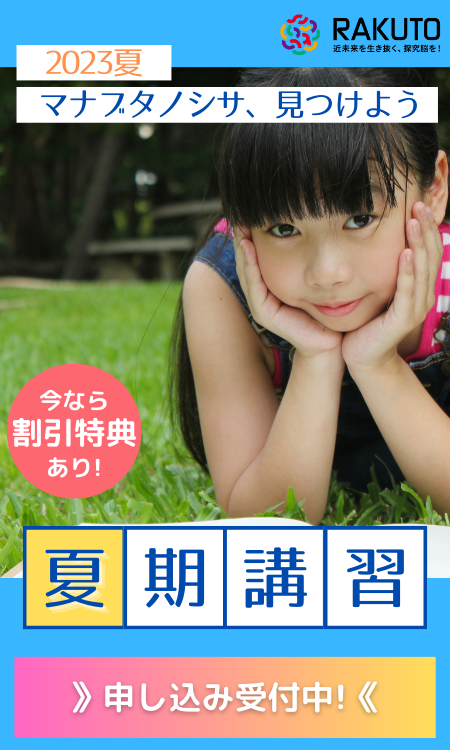目が四つもあった人がいたの?!

牛の肩胛骨(けんこうこつ)に刻まれた甲骨文字。漢字のもっとも古い姿です。占いの結果が刻まれています。(『漢字三千年の美展』にて展示されていたもの・著者撮影)
むかし,むかしのことです。
古代中国の帝王黄帝のもとで,史官という記録係に蒼頡(そうけつ)という人物がいました。
非常に観察眼が優れていた蒼頡は,ある日,地面についた馬や牛の足跡を見ていてふと気づきました。
これは馬の足跡。これは牛の足跡・・・馬や牛を直接見ていないけど,足跡の違いでそれが分かる。
これをうまく使えば,牛や馬のことを記号で表せるぞ・・・
そうして蒼頡は動物の形をもとにして,それらを表す記号を作り始めます。
そうこれが漢字の始まりだというのです。
観察眼が優れていた蒼頡は,なんと目が四つもあったとか?!
昔の中国には本当にすごい人がいたんですね!
漢字の国の人だもの
上に書いた話は,もちろん後世の創作がほとんどでしょう。
蒼頡という人物がいて,非常に観察眼に優れていたのはあったかもしれませんが,漢字がたった一人の人間の手によって生み出されたものとは今は思われていません。
中国の人も,「あれはあくまで伝説」という感じでとらえていることでしょう。
しかし,漢字が中国で生まれた偉大な発明であることには違いありません。
世界には4000から6000ぐらいの言語がありますが,そのうち,文字を持たない言語の方が圧倒的多数です。
独自の文字を持つ言語となるともっと減ります。
また,古代文明においては,漢字と同じぐらいの時期にエジプトのヒエログリフ,メソポタミアの楔形文字などが生まれていますが,いずれも滅びてしまった(使われなくなってしまった)文字で,3000年の時を経て使われているという点をとっても漢字の偉大さが分かります。
日本に漢字が伝わったのは5世紀ごろと言われています。今から1500年ほど前のことです。
もちろんそれ以前にも,たとえば「漢倭那国王」の金印が57年に日本にもたらされたとされているように,漢字というもの自体が日本には伝わってきていますが,その頃は,模様レベルでしか認識されていなかったと言っていいでしょう。
実際に「伝える」機能を持った記号としての「文字」として使われるようになるのは5世紀に入ってからのことと考えられています。
日本語と中国語では全く言語としての性質は異なります。
そのため,日本での漢字の使われ方,使い方は本家の中国とは異なるものがあります。
最初は記録は漢文でされていたのが,やがて,音だけを借りて日本語を表記する「仮名」という使い方を発明し(万葉仮名),それがさらに発展したのが,平仮名・片仮名です。
今も私たちの生活に深くかかわる漢字。
漢字のヒミツをちょっと調べてみるだけで,そこにはとても興味深い,面白い話がたくさん隠れていますよ。
漢字を楽しむイベントを開催
5月14日(日)に,RAKUTO神戸岡本校で漢字を楽しむイベントを開催します。
漢字の書き取りや読み方や意味の「お勉強」ではありません。
漢字の成り立ちのヒミツやそのほか,漢字の面白い話をたくさん知って,漢字のことを好きになるイベントだよ。
詳しいことを知りたい方,お申込みをご希望の方は,どうぞお知らせ「漢字を楽しもう」のページをご覧ください。