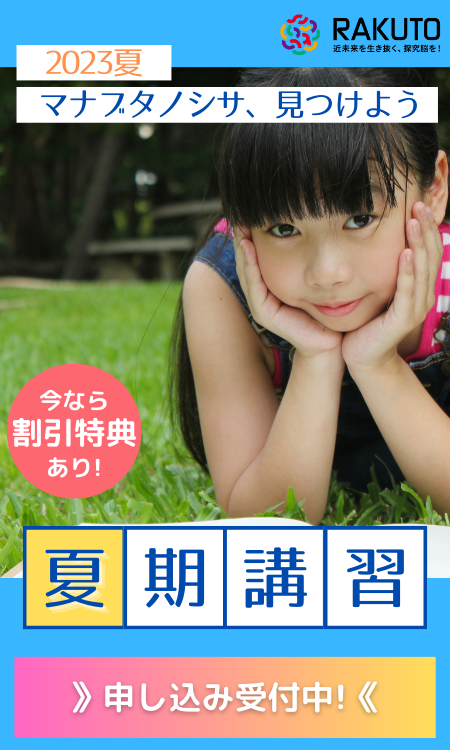「目玉焼き」と「たい焼き」は同じ仲間?
「目玉焼き」と「たい焼き」は同じ仲間?
みんなは「目玉焼き」は好きかな?
朝ごはんに毎日食べている?
そうか~,そんなに大好きなんだね。
ところで,この「目玉焼き」って名前,よく考えると面白いね。
だって「目玉を焼く」って書いてあるんだよ!?
もちろん,本当に「めだま」を焼いているわけじゃないね。
イラストみたいに,卵のようすがめだまに似ているから「目玉焼き」って言うんだね。
「たい焼き」はどうだろう?
これも,本当にお魚のタイを焼いたものじゃなくて,タイの形をしたお菓子だね。
面白いね。
本当は違うものなのにかたちが似ているからその名前がついているんだね。
メタファーという機能
さて,このような「形が似ている」というところに着目して表現する手法を「隠喩(メタファー)」と言います。
これはずっと以前は,いわゆる「文章表現の修辞法」,つまり効果的な文章表現の手法の一つとだけ考えられ,研究がされていました。
しかし,よくよく考えると私たちの身の回りにはありとあらゆるとこにメタファーがあふれています。
目玉焼きもたい焼きもそうです。
月見うどんはどうでしょう?
これも卵の黄身を満月に見たてたメタファーです。
よく似たものできつねうどんはどうでしょうか?
どこにもキツネは入っていませんね。
油揚げが入ったおうどんですが,「油揚げはキツネの大好きなもの」という関連性(厳密には隣接性)に着目した比喩の一種で,メトニミー(換喩)などと読んでいます。
私たちはどうして言葉を理解できるのだろう?
こうやってあらためて見直すと,私たちが言葉を理解するというシステムのふしぎを感じますね。
きつねうどんと言われても,きつねが入っているとは思いません。
月見うどんも,月見の時に食べるうどんとは違います。
あれ?月見団子は同じように丸いけど,こちらは月見の時に食べる団子ですね。
目玉焼きもたい焼きも「かたちが似ている」から「目玉」や「たい」が付きますが,「たこ焼き」はタコが中に入っていて,形はタコの形はしていません。
私たちは他の意味を持った言葉の結びつきでもしっかり理解するんですね。
このような「どのように私たちは言葉を理解しているのだろうか」というアプローチで言語を研究している分野もあります(認知言語学)。とても面白い学問のひとつです。
慣用句にもメタファーがたくさん
慣用句は,二つ以上の言葉がくっついて,新たに別の意味も持つようになったものです。
「骨が折れる」は,転んだり何かがぶつかったりして本当に骨が折れることもあれば,「たいへんな苦労をする」という意味でも使われます。
実際の意味ではなく,「骨が折れると日常生活にも支障がでるほどたいへんで,痛くて,つらくて」といったところの類似性に着目して,たいへんな状況に「骨が折れる」と使い始めたのでしょう。
「目を丸くする」も,びっくりした時に「目が大きく開いて丸く見える」ということからできた表現でしょう。
だれが言い出したのかわかりませんが,そのような表現がいつの間にか定着して,みんなが普通に使うようになれば慣用句です。
これからも新しい慣用句が生まれることはあるのでしょうか?
そんな慣用句を作るのはもしかしたら君かもしれないよ?
RAKUTOの春期講習2017の国語のテーマは「ことばのわざ ことわざ」だよ。
ことわざや慣用句をたくさん勉強して,自分でも新しいことわざや慣用句を作る楽しい時間だよ。
さあ,春期講習2017に君も参加しよう。
お得な早期割引も3月13日(月)まで。締切迫る!
お問い合わせもお気軽に!