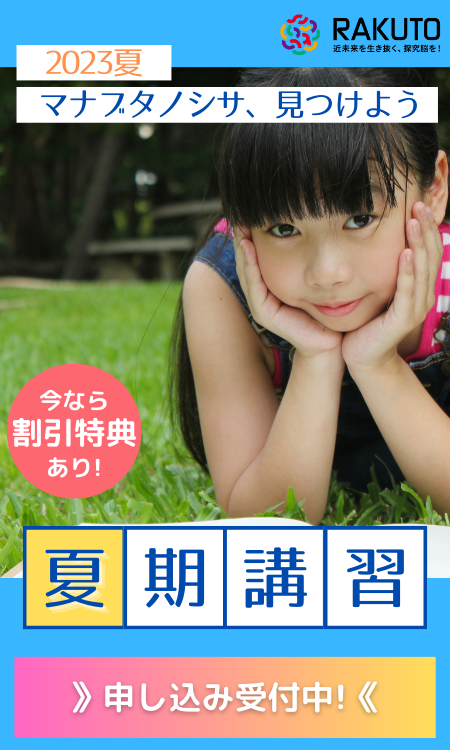語彙力をつける
 以前に「語彙力が決めて」だということをこのブログでも書いております。
以前に「語彙力が決めて」だということをこのブログでも書いております。
人の上に立てるかどうかの決定的な差が「語彙力だ」という話です。
実際に「出世したいかどうか」は別にしても,人生を豊かにするかどうかも,ひとえに「語彙力」に左右されます。
上にリンクを貼ったブログでは「語と語彙の違い」についてのご紹介をしました。
「語彙」の「彙」は集合体,という意味で,「語彙」は「ある特定の語の集まり」と考えたらいい,ということです。
理解語彙と使用語彙
「語彙」にはそんなわけでいろんな観点でのまとめ方ができますが,「理解語彙」と「使用語彙」という分け方もできます。
ほぼ文字通りの意味です。
「理解語彙」は「聞いて,読んでわかる語彙」で「使用語彙」は「実際に自分が言ったり書いたりするときに使う語彙」です。
ただポイントとしては「理解語彙が必ずしも難しいわけではない」ということです。
「俺」という語は,女性は普通は使わないでしょう。でも聞いて,読んで理解できますね。
つまり「理解語彙」です。
特別難しい語ではないですよね。
「理解できない語は使えない」ので,「理解語彙」の集合の方が「使用語彙」の集合より必ず大きくなります。
したがって,「語彙力をつける」には「まず理解語彙の集合を広げる」ということになります。
ことわざと慣用句
そういう観点から,「自分ではなかなか使えないけど,読んで聞いて理解したい」ものの一つが「ことわざ・慣用句」です。
似たような印象がありますが
ことわざ:昔から人々の間で言いならわされた,風刺・教訓・知識・興趣などをもった簡潔な言葉。
慣用句:二語以上が結合し,その全体が一つの意味を表すようになって固定したもの。
(いずれも『大辞林』から)
という違いがあります。
たとえば「骨が折れる」は文字通り「転んで骨折した」と言いたいときに使う一方で,「大変な苦労をする」という意味を別に持ちあわせています。これが「慣用句」です。
「旗を振る」も,「応援で旗を振る」こともあれば,「リーダーとしてふるまう」という意味にもなりますね。
ことわざは,「犬も歩けば棒に当たる」「花より団子」などですね。
ことわざの由来を知る
ことわざを知ることは,ただ語彙が増えるだけではなく,総合的な「日本の文化」を垣間見ることにもつながります。
人々が「昔から言い慣わしてきた」ということで,そこにはかつての日本の姿が現れてきます。
「紺屋の白袴」ということわざは,いまどき「紺屋」が身近にないので,すっと理解できないかもしれません。そういう意味では,ことわざの学習は骨が折れます。
教室で使っているとあるテキストに「六日の菖蒲,十日の菊」が紹介されています。
「時期が遅れて役に立たないこと」という意味なのですが,これを丸ごと覚えたところで何の役にも立ちません。なぜそれが「時期が遅れていることになるのか」を理解したいところです。
菖蒲は,端午の節句に使いますね。つまり「五月五日」に必要なもので,翌日の六日ではもう遅いよ,ということです。では菊はどうでしょうか?
今の日本では,ほぼ話題になることもない「節句」が関わるのですがどうでしょうか?
九月九日,重陽の節句です。重陽の節句で用いられるのが菊です。
『紫式部日記』や『源氏物語』などには出てきますが,八日の夜に菊を真綿で包み,九日の朝,その菊の香りいっぱいの夜露のしみこんだ真綿で体をぬぐうと無病息災となる…といういわれがあります。
これも十日では遅いわけです。
重陽の節句は知らなくても仕方ないなとは思いますが,今時の子は「こどもの日」は知っていても「端午の節句」は意外と知りません。こういうことわざを通じて逆に日本の文化や伝統を知るというきっかけにもなっているようです。
今度の春期講習の国語のテーマは「ことわざ」です。
たくさんのことわざ,慣用句と出会い,イメージをふくらませ,大いに遊びます。楽しく出会うのできっと子供たちの中で「忘れられない語彙」の一つとして残っていくことでしょう。
子供達と,どれだけ楽しくことわざや慣用句で盛り上がれるか。
今から楽しみでしかたがありません。
「ことばのわざ ことわざ」で楽しむ春期講習2019のご案内,是非ご覧ください。