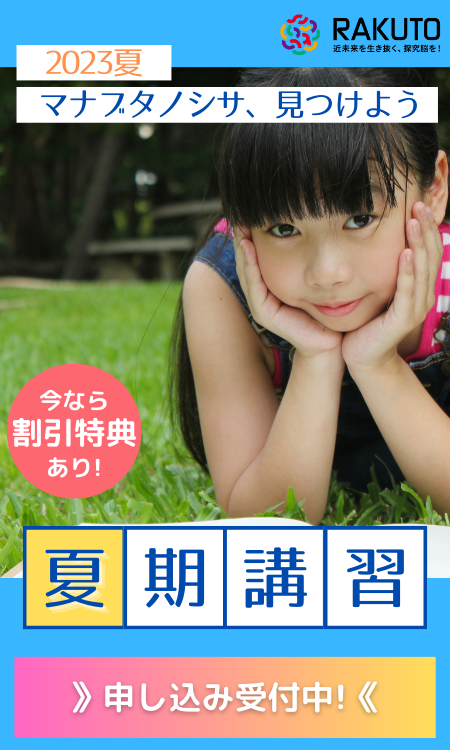星が動くのか地球が動くのか
 朝,太陽は東から昇り,南の空を通って,夕方,西に沈んでいきます。
朝,太陽は東から昇り,南の空を通って,夕方,西に沈んでいきます。
夜になれば,星が見えてきます。ずっと眺めていると,なじみの星座たちも,太陽と同じく,東から南を通って西に傾いていきます。
明け方には東の空が白々としはじめ,また日が昇ってきます。
昔の人々は,大地が動くということは全く考えられることではありませんでした。
太陽や星,月が東から西に動いて見えるのは,すべて天の方が動いているのだ,と思っていました。
いわゆる「天動説」です。
地動説 コペルニクス的転換
大地(地球)の方が動いている,と考えていた人はずっと昔にもいました。
特に紀元前3世紀ごろのアリスタルコスの考えは,太陽を中心として5つの惑星の動きを考えていて,のち2000年近く,彼の水準で考えた人はいないレベルです。
しかし,ほぼ世の中の学者の考えは天動説でした。
あらためて地動説を唱えたのがコペルニクスです。
16世紀の中頃のことです(日本では戦国時代真っ盛りの頃)
17世紀の初めに天体望遠鏡が発明されます。
ガリレオ=ガリレイは望遠鏡を使って月や惑星の観測をします。
月のクレーターのスケッチをのこしたり,土星の環も見ています。
木星には特に4つの大きな衛星(月)があることも発見しました。
イオ,エウロパ,ガニメデ,カリストの4つの衛星は,「ガリレオ衛星」とも呼ばれています。
ガリレオは,木星の周りを回る衛星の動きを観測していくうちに,月が地球の周りを回っていること,そして地球も太陽の周りを回っているということに考えがいたります。
ガリレオは地動説をはっきりと唱えますが,異端裁判にかけられ,地動説の撤回を迫られます。
その時に残した言葉とされるのが「それでも地球が動く」です。
※この言葉の訳はもちろん,そもそもつぶやいたかどうかも含めて諸説あります。
これはわずか400年ほど前の話です。
私たちにとっての当たり前は?
現代に生きる私たちは,地球が太陽の周りを回っている,ということを素直に受け入れています。
多くの観測結果がそのことを裏付けていき,科学的にこれが正しいとされたからですね。
科学の進歩は,疑問を抱き,現象を観察し,考察を加え,推論をより進めていくことによります。
残念ながら天動説から地動説が受け入れられるようになるには,ずいぶんと時間がかかりました。
多くの制約があったことも事実ですし,観測機材がなかったというのもあります。
大事なことは,多くの人たちが観察し,考え,観察し,考えということを繰り返してきたということです。
僕たちも考えよう,観察しよう
RAKUTOの冬期講習理科のテーマは,「地球から,宇宙から 天体を見てみよう」です。
太陽,月,地球の動きを身近なことや,モデルを使いながら一緒に観察し,考えていきます。
この世で最も大きなもの,それは宇宙です。
宇宙から私たちの住む地球を眺めていく。
想像力豊かに考えを深めていくことで,宇宙のロマンを感じていきましょう。
詳しくは「RAKUTO冬期講習」のページをご覧ください。