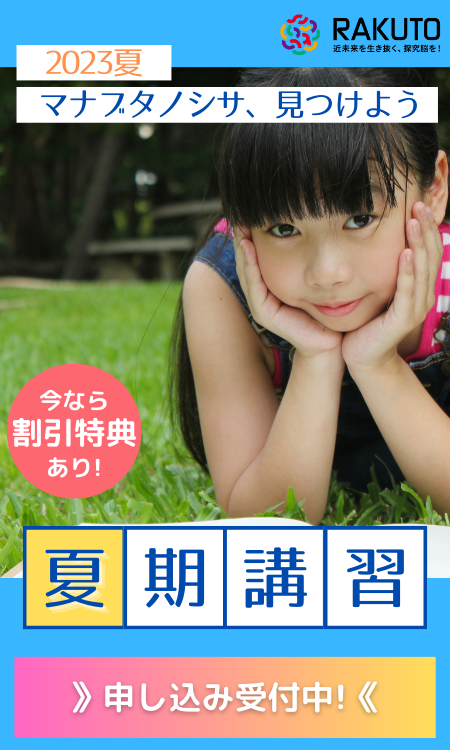AI時代到来の不安にあおられない
 AI・人工知能,機械学習に関する技術の発展は目を見張るものがあります。
AI・人工知能,機械学習に関する技術の発展は目を見張るものがあります。
そのため,
AIに仕事を奪われる
AIのせいで仕事がなくなる
といった「便利なAIのせいでむしろ将来が悲惨なものになる」とまで感じさせられるような主張もよく目にします。
人類は,家庭内手工業から工場制手工業,工場制機械工業とどんどん生産形態を発展させ,社会も発展してきましたが,「短期間での技術の発展」というのは過去とは比べ物になりません。
その点では不安になるのもわかります。
しかし,本当にAIのせいでとたんに人々が路頭にまようような時代になるのでしょうか?
単純な繰り返し作業などは,AIなら長時間やっていてもミスもなく,作業効率もいいでしょう。
そういうのはこれまでも一定レベル機械に任せてきたのが,さらに大々的にAIによって処理されていく,という時代にはなるでしょう。
むしろ「人が苦手とするような分野はどんどん代わりにやってくれて辛い仕事から解放される」ぐらいに思いたいものです。
新しいものを創り出す力
一方で,頭を使うような,知恵を使うような,あるいは何かを生み出すような分野はまだまだ人の出番でしょう。
ただ,「新しいものを創り出す力」があればいいんだよ,といわれても,
「創造力はどうしたら身につくのだろうか」
ということが分からないから多くの人が不安にさせられているのです。
子供たちの未来は子供たちが切り開く
小学生ぐらいのお子さんをお持ちの親御さん方は,今までの価値観や概念がうまくそのまま機能しないことを目の当たりにしてこられた世代です。
良い中学,良い高校,良い大学を出て,良い会社に就職すれば人生は順風満帆
そんな価値観は今時誰も信じていないでしょう。
「良い学校」の「良い」ということの基準も多様になってきました。
「良い会社」も何が「良い」のでしょう?
そもそも「会社に入る」ということがいいの?
「起業」ということも有力な選択肢になってきています。
どうしたら「順風満帆」といえるのだろうか?
実は今はもうすでに「多様な価値観の中で手探りで生き抜いていかないといけない」時代なのです。
大事なことは「手探りをすることをいとわない」ということや「どうすればいいかを考え抜く力」だったりしますね。
自分の人生を人任せにしないで,自分であれこれ考えて納得した選択をする。
その積み重ねが今後ますます必要になってきます。
基本は「好奇心をはぐくみ育てること」
大学入試改革についても,迷走しているイメージが強く,将来の見通しが立ちにくいのも事実です。
そんな中で我が子をどのように教育すればいいのだろう?と頭を悩ませる親御さんも多いことでしょう。
RAKUTOの子供たちを見ていて思うのは,子供たち自身がすでに十分に力を持っているので,まずはそれを信じよう,ということです。
子供たちは無限の可能性がある。
これは事実です。
でも,可能性を可能性のままに閉じ込めてしまってはいけません。
可能性は「試す」ということをしていかないと見出されないままになります。
子供たちを力を信じ,可能性を見出すために必要なのは,子供たちの好奇心を刺激し,そのアンテナの向く方向に一緒に歩んでいくことだろうと思います。
「一緒に歩む」というのは,
子供が楽しいと思っていることを一緒に楽しむ
子供が初めて知って驚いたときには一緒に驚く
大人が初めて知ったときにも驚きを伝える
そういったやりとりで「知ること,学ぶこと」のわくわく感が「これ以上に楽しいことはない」と思えるようになります。
また,同時にいろんな刺激を発信し続け,あらたな方向も子供たちが見つけ出せるようにしていく,ということも大事ですね。
大人が楽しんで欲しいことを押し付けるのではありません。
「これが楽しいのなら,こういうのも楽しめるかも?」
「こっちは苦手なら,こっちなら合うのかな?」
そういう感じで,あくまで子供主体で可能性を見出そうとすることができれば,きっと「その子にこそぴったり合うもの」が見つかることでしょう。
RAKUTOの授業は好奇心を刺激し考え抜く力を身につける
RAKUTOの授業は,HOP,STEP,JUMPの3ステップ。
発達年齢に応じて,好奇心を刺激し,一緒に観察し,結果を予測し,どうしてそうなるかを考え抜きます。
その繰り返しで,自分で課題を見つけ,考え,解決していく力の基礎力をしっかり養います。
小学校を卒業後,いろんな進路に進んでいきますが,どこに行っても,きっとRAKUTOの子供たちは自分たちの力で道を切り開いていってくれるに違いない,そう信じています。