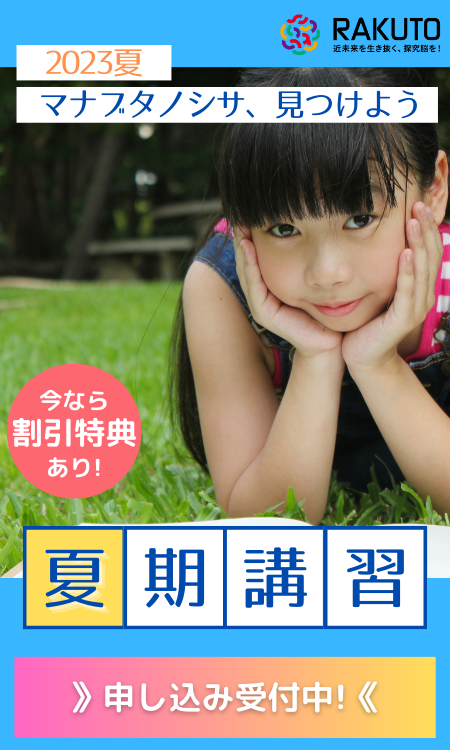宇宙へのあこがれの原点
今回は筆者の子供の頃の体験をお話します。
3年生か4年生の頃に,学研の「ひみつシリーズ」の『星と星座のひみつ』を買ってもらいました。「ひみつシリーズ」は大好きな本でしたが,特にこの『星と星座のひみつ』は何度も何度も読み返しました。
宇宙,星と星座,神話など,そうしたことに夢を膨らませた時期でした。
まだ天体望遠鏡はおろか,双眼鏡すら持っていない小学生でしたので,「天体観測」と名の付くことは何もできなかったのですが,初めて「天体観測」をしたのが「1981年7月31日の部分日食」でした。
夏休みでしたので,昼間でもゆっくり観測できました。
きちんとした知識がなく身近に指導してくれる方もいないので,濃い色の下敷きを通してみるという,今だと怒られそうな方法でしたが,周りの景色,何分かおきに変わっていく太陽の位置,そして見た目で感じた欠け具合を色鉛筆で記録したのを覚えています。
その後,ハレー彗星の接近の時にはようやく双眼鏡を手に入れ,大学生になってからは天文サークルに所属し,木星や土星の眼視観測を熱心にやることになりますが,その時の原点は,「部分日食をスケッチした」というこの時の体験にあります。
12月26日には部分日食が見られる
日食は,太陽と地球の間に月が通り過ぎることで起きる現象です。
地球は太陽の周りを回り,月は地球の周りを回っています。
その回っている面(公転面)は,同じ平面ではなく微妙にずれているので,いつもぴったり重なるということはないのですが,地球から太陽を見た方向に月が通り過ぎるように重なることが稀にあって,その時に日食が起きます。
今年は部分日食ですが,1月と12月の年2回も日本から日食が見られるという珍しい年です。
12月26日の部分日食は,日本全国で見られますが,東日本では少し欠けたまま太陽が沈んでいきます。神戸近辺では15時半ごろに最も欠けて見えます。
(画像:国立天文台 https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2019/12-topics03.html)
日食や月食は,太陽,地球,月の動きをダイナミックに感じさせてくれて,そして,比較的簡単に見ることができる天文現象です。
実際に天文現象を観察することで,宇宙の広さを感じてほしいものです。
一緒に部分日食も観察しながら,太陽・地球・月の動きも勉強しよう
RAKUTO冬期講習2019のテーマは「地球から,宇宙から 天体を見てみよう 太陽・地球・月」です。
偶然ですが,初日の授業開始時間とこの部分日食の最大食分(最も欠けて見える時)の時間が近いので,みんなで一緒に日食の観察もしようと計画中です。
部分日食は簡単に観察できるとは言っても,太陽の光はとても強烈です。
肉眼で見ると目を傷めてしまいます。きちんとした日食観察用のサングラスをつかうなどして,適切に観察します。思わぬ「おまけ」付きの講習になりそうです。
その他の科目など,冬期講習の詳しいことは「RAKUTO冬期講習」をごらんください。