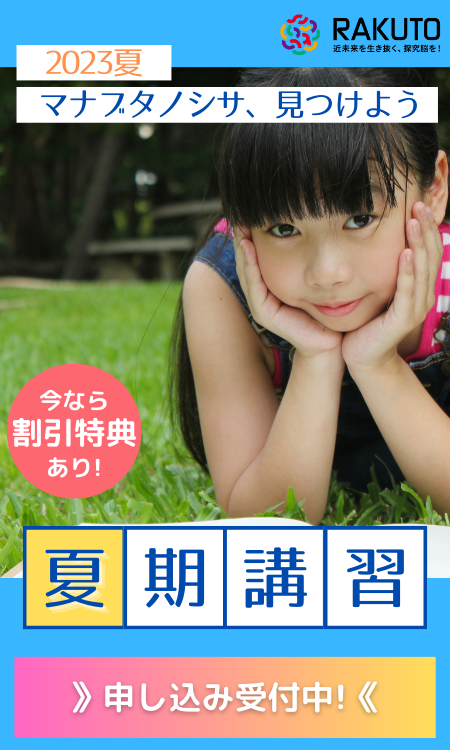光が見えない真っ暗闇
みなさんは,本当の真っ暗闇を体験したことがありますか?
子供の頃,山の中にある父親の実家に帰省した時の夜の暗さは今でも忘れません。
晴れていれば,満点の星空ですが,曇っていると星の光すらありません。
街灯もありません。玄関や家の周りにも明かりはありません。
夜中にトイレに行きたくなって,家族を起こさないようにとそっと布団を抜け出したのはいいのですが…
トイレはなんと家の外(田舎の古い家ではよくあること)
完全な真っ暗闇の中,足を少しずつ出しながら,手探りで…途中からほとんど四つん這いでトイレに向かったのを思い出します。
見ているのに全く「光」が入ってこない,全くの闇というのはなかなか怖いものです。
自分の身体すら見えないので,どこまでが自分かどこから外なのかすらわからないぐらいです。
私たちが生きているのは,「光」があってこそですね。
見える光と見えない光
さて,光は見える…光のおかげで見えるのですが,光ってなんでしょう?
みなさんは,赤外線や紫外線という言葉は聞いたことがありますか。
遠赤外線ヒーターとか紫外線防止の日焼け止めなどなどで聞いたことはありますね。
その赤外線や紫外線って見たことはありますか?
実は,この「赤外線」や「紫外線」は,「人間の目に見えない」ものなんです。
光は電磁波の一種なのですが,ある特定の波長だけが人間の目に見えます。
それを「光」と呼んでいます。
光は,プリズムを通してみるといくつかの色に分かれます。
「虹」は赤,橙,黄,緑,青,赤などのいくつかの色に分かれて見えていますね。
色と色の境ははっきりしません。人によって細かく分ける人はいるでしょうし,同じところを指しても,
違う色だと思う人もいるでしょう。
ただ,端が赤と紫というのは変わらないでしょう。
この赤より長い波長のものを「赤外線」と言います。「赤の外側にある」ということだったんですね。
となると,紫外線は…そう,「紫より外側,つまり紫より短い波長のもの」が「紫外線」です。
人間の目に見えないところが赤外線,紫外線です。
その見えない外側より内側の波長のものを「可視光線」,つまり「目に見える光」というわけですね。
光って面白い
赤外線,可視光線,紫外線とあって,見えているもの,見えていないものがあるって面白いですね。
光の性質についていろいろ探ってみると,「見えるのが当たり前」と思っていたことが,意外にそうではないことに気付きます。
RAKUTOの春期講習の理科のテーマは「光と色」です。
どうして空は青いの?その空が,夕がたには赤くなってしまうのはなぜ?
そんな秘密にせまる楽しい時間です。
そして,工作では,自分の手でいつでも虹が見られる「虹のキャンパス」をつくります。
どうして,なぜ?を考えて,自分の手で作って,楽しい時間を過ごすから,勉強が大好きになってしまう。
そんな楽しい春期講習です。