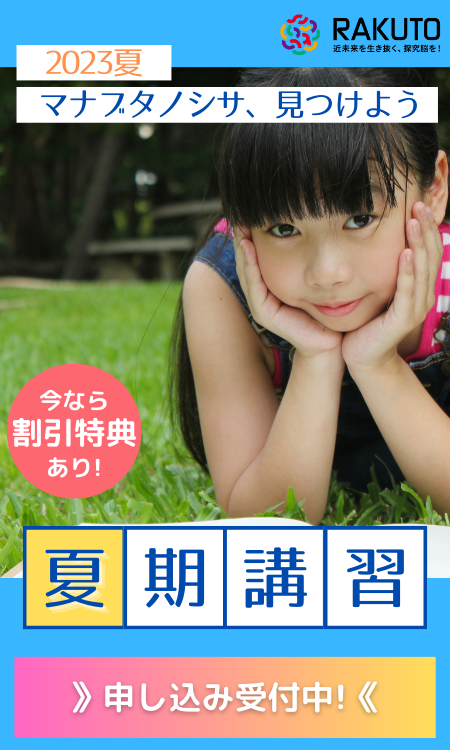人類の過去を探ってみよう
人類の歩みを調べるにはどうしたらいいのでしょうか?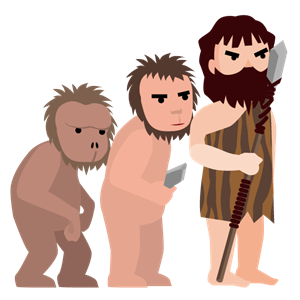
古文書を開いてみてはどうでしょう。
すぐに思いつく方法ですね。
日本に残る数多くの古文書は,古いものでもその多くが美しい漢字で書かれているので,専門的な知見によって読み解くのはさほど困難でもないでしょう。
とは言え,それらは5世紀,6世紀以降の話。4世紀以前となると途端に困難になります。
実はそれ以前の時代については,日本のことを直接書き残した資料が日本にないからです。
卑弥呼の時代などは中国の『魏志倭人伝』や,もっと以前の『後漢書東夷伝』などにも日本について書かれた記述は見つかりますが,極端に少なくなり,謎がたくさん残ってしまいます。
だから「邪馬台国はどこにあったのか(いや,そもそもなかったのか?)」など,議論は尽きないのです。
文字のない時代のことはどうやって調べるの?
世界的に見ても,文字による記録が残っているエリアは限られています。
時代も限られています。
古いものなら,エジプト文明にはパピルスにヒエログリフ(象形文字)で書かれた史料があります。
それでも3000年前,4000年前です。
ホモ・サピエンスの初期は約20万年前。「人類」と私たちが考える祖先が動き出した頃から考えると,文字による記録が残ってない時期の方がよほど長いのです。
そうした「文字の記録のない時代」のことを「先史時代」と呼んでいます。
文字が発生して以降は「有史時代」と呼びます。
先史時代のことはモノから考える
先史時代の人々がどのように生きていたか。
それを探る手掛かりは,残された「モノ」から想像するしかありません。
たくさんの考古学的な発掘調査によって,数多くの遺物が発見されています。
例えば道具を考えてみましょう。人間と動物を分ける大きな要素が「道具」です。
最初の頃に作られた素朴な打製石器。
石と石を打合せてつくっていた石器がある時代が旧石器時代です。
やがてその石器づくりが精巧になっていきます。磨製石器の登場です。
石器以外にも,銅器,鉄器が発明,製造されていきます。
どのようにそういった道具を作っていたのでしょうか?
誰がその道具を使っていたのでしょうか?みんな同じように所持していたのでしょうか?
数が少ない内はもちろん「ステイタス」になっていたはずです。
権力の象徴ともなったでしょう。
そのように道具一つ一つを丹念に追いかけながら,文字には残されていない時代に,人々がどのように生きてきたのかを探っていくのです。
キーはイマジネーション
昔,遺跡の発掘現場で,調査員の方と話していたときのことです。
その現場で見つかった2センチほどの土器の欠片を手にして(イメージ的には箸置きぐらいのもの),「これはこの土器のこの部分でしょうね」と本の中の写真を示しておっしゃいました。
その土器は大きさ30センチか40センチはあろうかという土器です。
ほんの数センチの欠片で「この欠片はこの土器のこの部分」と言い切れる想像力に驚きました。
隣に似たような欠片があったので「これも同じ土器ですか?」と聞いたら「ああ,これはこっちですね」と形も大きさも違う土器を指されました。なぜその区別がつくのか素人の私にはまったくわかりませんでしたが,専門家には見える違いがあるのでしょう。
彼らはまさにイマジネーションのプロだったなと今も思います。
旅カルタをつくろう!歴史を旅するんだ。
RAKUTOの冬期講習2017の社会のテーマは「歴史」がテーマ。
古代に焦点を当て,その時代の生活,人々の暮らし,生きる知恵を学び,歴史の面白さを体感します。イマジネーション豊かに想像し,そしてその楽しさをカルタ制作を通して形にしていきます。
そんな楽しい冬期講習のお申し込みは,「冬期講習2017」のページから!